-
Services
Hospital Management - Consulting Services
Publications
- Our Consultants
- Case Studies
- About Us
-
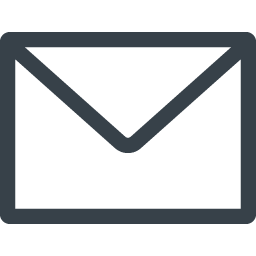
2021年03月17日

医療ビッグデータが新型コロナウイルス第3波の「教訓」を示す連載の3回目のテーマは、新型コロナ患者に入院医療を提供する「大病院の受け入れ能力と役割分担」。400床を超える大病院であっても、1日に受け入れられる入院患者の中央値が約6人と10人にも満たない状況が浮き上がってきました。
グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)はこのほど、「第3波(2020年11~12月)」の医療ビッグデータを分析。分析条件は以下の通り。全国の急性期病院(DPC対象病院)の約3割のデータという計算になります。急性期病床の機能を持たない病院は分析対象に含まれておらず、急性期病床に特化した分析であるという点に留意ください。
今回のテーマに関する新たな独自のデータ分析結果を見る前に、前提条件としてある「病床過剰なのに病床ひっ迫のなぜ」の根本的な課題を確認します(詳細は『医療崩壊の真実』参照)。
これについてGHC代表取締役社長の渡辺幸子は、「日本は人口あたりの病床数が断トツ世界一。日本の医師数は人口千人当たり2.5人(米国と同レベル)でOECD平均3.5人より少なめ、看護師数は人口千人当たり11.8人とOECD平均以上です。病床数と病院数が多すぎることによって、病床あたり医師・看護師数が世界で最も少ない結果となっています。つまり医療従事者が分散しており、各病院の医療従事者が“薄い”ため、どの病院もコロナ患者を受け入れられるキャパシティーが小さすぎるのです。そのため、すぐに『病床ひっ迫』との指摘を受けやすい状況になってしまうのです」と説明します。

上記は当社がOECD(経済協力開発機構)データを用いて独自に分析した結果です。人口1000人当たり病床数と同じく人口1000人当たり医師数のデータをかけ合わせて、「一病床当たり医師数」を割り出しました。
これによると、日本は米国よりも圧倒的に病床数が多いため、一病床当たり医師数は日本0.2人なのに対して、米国は0.9人とその差は4倍以上になります。つまり、米国で1人の医師が1日当り1人の患者を診ているところを、日本では1人の医師で1日当り4人以上の患者を診ている状況であることが分かります。手厚い医療と評されるドイツにおいても、日本が0.2人なのに対してドイツは0.5人とその差は2倍以上です。
この背景は、日本は他国よりも患者が多いからではなく、日本の急性期医療の在院日数が16日(2017年度)と他のOECD諸国と比べて約2.5倍と長い状況があるからです。これは、医療従事者の分散によって診療密度が薄いため、在院日数が長引く傾向と、病院経営を考えると在院日数を延長化して採算をとらざるを得ない2つの要因が考えられます。
「病床過剰なのに病床ひっ迫のなぜ」の根底に「医療資源の分散」があります。その中で、コロナ確保病床は急性期病床のうち3.4%と低水準のまま推移しているのです。

今回の新たな独自データ分析の結果はどうか――。
「第3波」に限って、病床規模ごとに1日当たりで受け入れている新型コロナの入院患者数の中央値を確認したところ、大規模病院であっても1日に受け入れられる入院患者数が10日にも満たないという実態が明らかになりました。
新型コロナの入院患者に対応する主な病床機能は、軽症あるいは中等症であれば一般病床、重症であれば集中治療室(ICU)など「ユニット」(「HCU=高度治療室」「ER=救急救命室」含む)になります。一般病床のみ▽ユニットのみ▽一般病床+ユニットの両方――の3つのパターンごとに、病床規模別でそれぞれ1日平均コロナ患者数を確認したところ、中央値で「一般病床+ユニットの両方」のパターンにおいて、400床以上では6.1人、200~399床3.8人、200床未満2.2人――という結果でした。400床以上の上位75%タイルでも1日平均10.8人です。
「第3波」の最中でも10床以上稼働させていた病院が少ないという状況について渡辺は「医療資源の分散により、200床未満の病院はもちろん、400床以上の病院であっても10床以上稼働できる病院が少ないことが改めて分かりました」としています。

病院個々のキャパシティーの課題に加えて、病院間での役割分担も大きな課題の一つです。例えば、重症患者は400床以上、軽症患者は200床以下など病床規模別で役割分担を明確にすることで、効率的かつ安全性の高い入院医療を提供することができるためです(本来、病床規模だけで病床機能を定義できず、医療従事者や治療機器などの医療資源の整備をみる必要があります)。
しかし、今回の分析結果からは、こうした病床規模別での「層別化」においても課題が残されていることが分かりました。
以下は「第1波」から「第3波」までの重症度別入院患者の推移を、病床規模別で見たものです。どの期間においても、400床以上の多くの病院で、中等症患者および重症患者だけではなく、軽症患者もかなり多く受け入れている状況が見て取れます。ここでは公立病院を取り上げていますが、この傾向はどの設立母体でも変わらない傾向です。

さらに病床規模を縦軸に、設立母体を横軸にしたマトリック上の各群を、重症度別患者で分けた円グラフで示し、それぞれの具体的な割合を確認しました。これによると、どの群においても軽症から重症まですべての重症度の患者を受け入れている傾向にあり、「層別化」が進んでいない状況が明らかになりました。大学病院でも4分の3が軽症含めてすべての重症度を見ている状況です。

これについて渡辺は「各病院の受け入れキャパシティーに限界がある中で、病院間の役割分担を明確にする層別化の推進は、近隣病院間での連携はもちろん、三次医療圏まで含む広域連携が不可欠。そのためには、都道府県ベースで情報共有するためのコントロールセンターの存在が望ましい」と指摘しています。
また、医療連携とそのための情報共有の仕組みは、今回の新型コロナに限らず、あらゆる疾患においても重要です。渡辺は加えて「医療連携とそのための情報共有は、コロナだけの問題ではありません。平時にこの問題に十分対応できていなければ、コロナのような有事に必要な医療連携が機能するはずがありません」とも付言しています。
連載◆データが示す「新型コロナ第3波」の教訓
(1)入院期間10日超の軽症患者が44%
(2)軽症患者の半数が「重症化リスク低い」
(3)大病院の入院上限10人未満が多半
(4)続く感染症患者の半減、がん受診抑制に注視を

株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパンの代表取締役社長。慶應義塾大学経済学部卒業。米国ミシガン大学で医療経営学、応用経済学の修士号を取得。帰国後、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンサルティング事業部などを経て、2003年より米国グローバルヘルスコンサルティングのパートナーに就任。2004年3月、グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン設立。これまで、全国800病院以上の経営指標となるデータの分析を行っている。近著に『医療崩壊の真実』(エムディーエムコーポレーション)など。

株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパンのコンサルティング部門コンサルタント。慶應義塾大学文学部卒。医療介護系ニュースサイトを経て、GHCに入社。診療報酬改定対応、集患・地域連携強化、病床戦略立案などを得意とする。多数の医療機関のコンサルティングを行うほか、「日本経済新聞」などメディアの取材対応や、医療ビッグデータ分析を軸としたメディア向け情報発信を担当。日本病院会と展開する出来高算定病院向け経営分析システム「JHAstis(ジャスティス)」を担当する。
| 広報部 | |
 | 事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。 |
Copyright 2022 GLOBAL HEALTH CONSULTING All rights reserved.