2009年01月07日
一番は、千差万別の患者さんの話を聞くこと――聖路加国際病院・中村先生
 聖路加国際病院●ブレストセンター長・乳腺外科部長 中村清吾先生
聖路加国際病院●ブレストセンター長・乳腺外科部長 中村清吾先生 今回は、
聖路加国際病院の中村清吾先生にインタビューさせていただきました。中村先生といえば、乳がんの名医として有名です。“名医”と言われることについて、聖路加国際病院で行っているチーム医療についてなど、お話をお聞きしました。
――先生は、書籍やインターネットなど、さまざまなメディアで、乳がんの“名医”と称される機会が多いと思います。先生にとって、名医とはどういう人を指しますか? 名医なのか、迷医なのか…(笑)。名医とは、自分で思うのではなく、他の人が考えることですのでわかりませんが、常に気をつけていることはあります。一番は、患者さんの立場で話を聞くこと。医者になった当初、臨床現場に出て、患者さんは十人十色だなと思いました。そして10年ほど経つと、百人百様だなと思うようになりました。そして今は、千差万別だと感じています。
患者さんは、一人ひとり抱えている問題も、価値観も、バックグラウンドもとにかく違いますから、そのことを意識して話を聞くことが大切です。どんな治療法がふさわしいかは、最終的には個人の価値観。生存率だけの問題ではないわけです。効果と副作用のバランスもそうですし、高騰しつつある医療費の問題もあります。
――お一人お一人に十分に時間をとることは可能ですか? 患者さんによって5~10分で終わる方もいれば、30分、なかには1時間近くかかる方もいますね。ですから、外来の予約時間が、どんどんずれてしまうことがあります。でも、後のスケジュールを気にしながらでは、よい診療はできません。。
私の外来担当日は月曜日と木曜日で、大抵、夜遅くまでかかってしまいますので、予定はいれないことにしています。
――ところで、聖路加国際病院では、アメリカのM.D.アンダーソンがんセンターと姉妹病院として提携されているそうですね。日本とアメリカではどのようなところに違いを感じますか? 人事交流とリサーチ、患者さんの紹介を主な柱に、提携を行っています。違うのは、医療そのものにかけるお金、そして関わっているスタッフの数ですね。一見、無駄に見えるかもしれませんが、やはり一定以上の人が関わらなければよい医療は提供できません。いくらITによる効率化が進んでも、医療の本質は人と人とのかかわりあいです。たとえば、ITが進化して、ふさわしい治療を選べるようになったとしても、その“人”にふさわしいかは別問題です。
がんを治す、いい医療を提供するには、医師や看護師、薬剤師などはもちろんですが、生活を支えるソーシャルワーカーや、死生観や生き方を教えるスタッフなども大切です。自分の死について考えなければいけないという現実に直面したときに、その対処法を語ってくれる人が日本にはほとんどいません。私たちの病院では、チャプレンがまさにその役割を担ってくれていて、回診のときはいつも一緒に行ってもらっています。
――まさにチーム医療ですね。ボランティアのスタッフもチームの一人として参加されていると聞きました。 はい。がんのサバイバーの方も参加してくださっています。同じがんの経験者として患者さんに接していただいている方もいますし、院内の案内役、エスコート役としてボランティア活動をされている方もいます。また、がんの告知をされてからまったく違う生き方をされる患者さんもいらっしゃいます。
実は私の母は心筋梗塞で亡くなりましたが、病院に通ったことはないくらいに健康な人でした。倒れて病院に運ばれて、初めて診察カードをつくったものの、到着後30分ほどで亡くなりました。ですから、自分の死について考える時間はまったくなかったと思います。ただ、肺がんで亡くなった父の場合は、逆に、がんを告知されてから、余命を考える時間が十分にありました。残された時間を充実して過ごせるように、私も京都や松山に学会に行った際には一緒に連れて行ったりしました。
母のようにほとんど苦しむことなく、死を意識するまもなく亡くなるのと、父のように治療の苦しみはありつつも、最期の生き方を自分で考える時間が残されたうえで亡くなるのと、どちらがよいかはわかりません。ただ、両親の死を身近で見届けたことは、私にとって1つの大きな転機になりました。がんにならない生き方を支援することはもちろんですが、がんにかかった患者さんに、その人が望む生き方を支援することも非常に大事なんですよね。

| 広報部 |
 |
事例やコラム、お役立ち資料などのウェブコンテンツのほか、チラシやパンフレットなどを作成。一般紙や専門誌への寄稿、プレスリリース配信、メディア対応、各種イベント運営などを担当する。
|
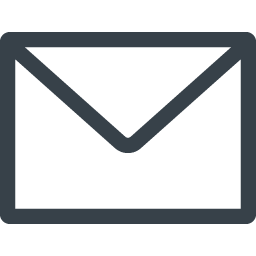
 聖路加国際病院●ブレストセンター長・乳腺外科部長 中村清吾先生
聖路加国際病院●ブレストセンター長・乳腺外科部長 中村清吾先生
